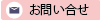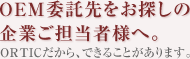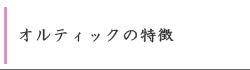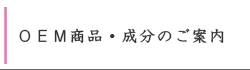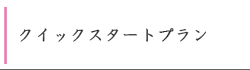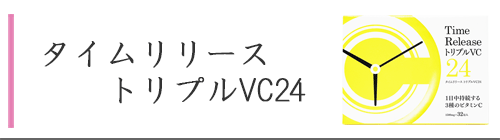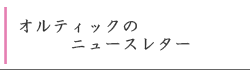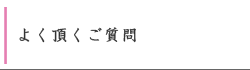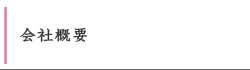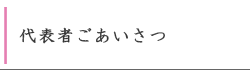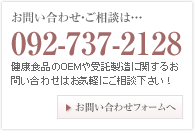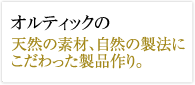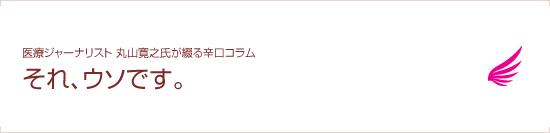現在のページ:TOPページ > 医療ジャーナリスト丸山寛之氏が綴る辛口コラム「それ、ウソです。」
露風の母の白内障
昭和二十九年秋、白内障になったかたは、長男の道夫とともに京橋のメガネ店に出かける。回復の望みなしと診断されたため、道夫に頼んで帰途、国会議事堂へ立ち寄る。(竹内道夫「<赤とんぼ>の母」=『毎日夫人』1998年2月号)
「かた」とは、北原白秋と並び称された詩人、三木露風(本名・操)の生母である。明治22年16歳のとき、兵庫県の銀行の頭取に懇望されて彼の息子に嫁いだが、夫の身持ちが悪く、幼児二人(操と勉)を残して離別。上京して就学、看護婦になり、明治35年、再婚。新聞記者の夫の勧めもあり東京婦人禁酒会を結成、禁酒運動を推進し、その後は婦人参政同盟に加わり、活動した。
そのような女性が晩年、白内障を患い、「回復の望みなし」と」「診断」されたというのだが、なぜ「メガネ店」なのか?
白内障は、目の水晶体(カメラでいえばレンズに当たる)が、白く濁ってくる病気だ。進行するにつれて視力が低下し、ついには失明する人が、昔は多かった。しかし、いまは濁った水晶体を取り出して、人工の眼内レンズを入れると、またハッキリ見えるようになる。あの百寿姉妹の妹、ぎんさんも、その手術を受けて、「ごはん粒がよーく見えます」と、テレビの取材に笑顔で話していた。
昭和29年当時には、現在とは術式は異なるものの、すでに水晶体の摘出手術が行われていた。
メガネ店の帰途、国会議事堂に立ち寄った、かたは、正門から構内に入ると、「婦人参政運動のさまざまな思いが脳裏をよぎったのか、二、三歩進むと、突然、その場にうずくまり号泣した」という。まだ完全失明には至っていなかったのだろう。だったら、なぜ、メガネ店ではなく、しかるべき専門医の診療を受けなかったのだろうか? 東大の看護婦養成所を出て多年、看護婦の経験があり、「婦人参政権と公民権の獲得、男女平等の制度改革及び家庭の平和向上」を掲げ、雑誌『女権』を創刊したほどの人にしては、いかにも目のない選択ではなかったか。
8年後、かたは89歳で永眠。通夜の晩、露風は、「弟妹に懇願して亡母と添い寝をしたが、これは六十八年間ずっと抱き続けていた夢であり、露風の息づかいが、かたの寝息のように感じられたという」。
露風の「赤とんぼ」の歌は、5歳のとき生別した母恋いの思いをうたったものといわれる。…